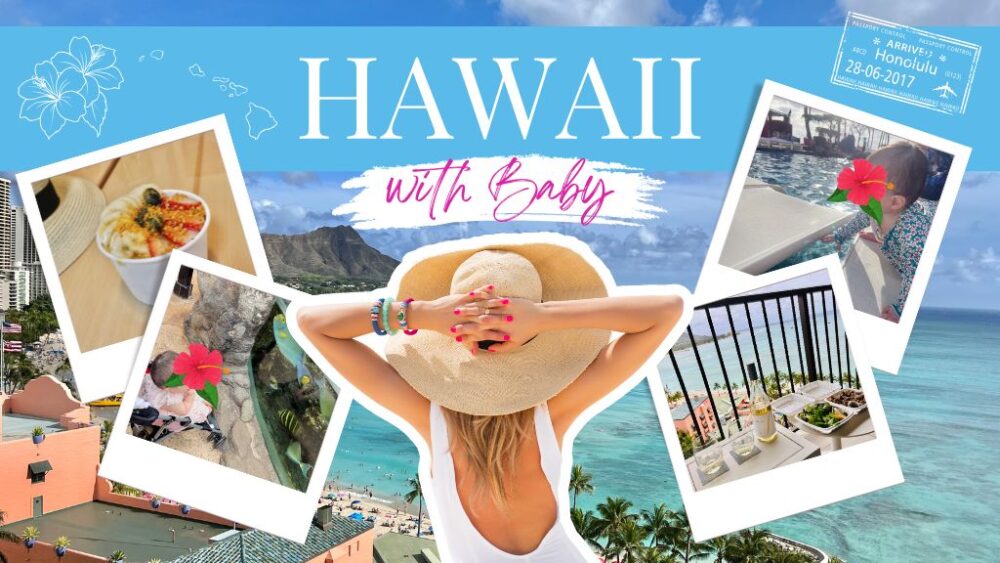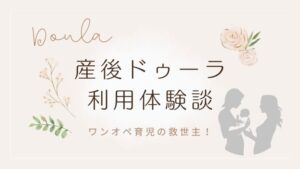生後4ヶ月を過ぎると少しずつ意識し始める離乳食。一般的に生後5~6ヶ月から開始し、それまで母乳やミルクしか飲んでいなかったベビーが初めてそのほかの食べ物を口にし始めます。
親としては寂しいけれど、ベビーにとっては味覚の世界が広がる素晴らしい体験ですよね
一方で、作るのが大変なのに全然食べない!などの苦労話を聞くことも。
今回は、港区の保健所で実施する「はじめての離乳食教室」に参加したので、その内容の一部をご紹介します。
 Serena
Serena栄養学の知識があっても知らなかった内容が盛りだくさんでした!
「はじめての離乳食教室」に参加しました
今回は、港区でママパパ対象に開催される「はじめての離乳食教室」に参加しました。
当日は、みなと保健所8Fの大会議室で並べたマットの上に座って聴講する形で、私が行った時は6組ほどが参加していました。
感想ですが、テキストに沿って進めるのかと思っていたのですが、専門的な内容が多く、ネットやパンフレットから得られる情報以上のことがたくさん知れてとても良かったです!細かい注意点なども多く聞けたので、離乳食を進める自信がついた気がします
備忘録的に、私がためになった情報をメモしておきたいと思います。
離乳食の進め方:ためになった情報
離乳初期(生後5~6ヶ月・ゴックン期):1日1回
- 離乳食スタートの目安
-
- 「生後5~6ヶ月ごろ」「首がしっかりすわり寝返りができる」「支えれば座れる(5秒以上座れる)」「食物に興味を示す」「スプーンを押し出すことが少なくなる(=スプーンを入れて上唇が下りる)」。
- 開始時刻は病院に行ける時間であれば大丈夫(赤ちゃんのアレルギーは即時性なのですぐに症状が出る)。
- 離乳食のエネルギー配分
-
- 離乳食を始めてすぐの頃は母乳:離乳食からとるエネルギーの割合はまだ9:1ほど。9ヶ月頃(3回食)を境に配分が逆転し、離乳食からとる栄養が大事になる。
- 離乳初期について
-
- 舌は前後に動くだけなのでポタージュ状~プレーンヨーグルト状にする。
- 10倍粥にこだわらなくとも、最近は5~7倍粥を赤ちゃんが食べられるようにお湯で調整しても良いと言われている。それまでは乳首を咥えて飲んでいた(口が開いている状態)ので、唇が閉じずに口からこぼして当たり前。
- 進め方のポイント
-
- 離乳食で腸内は激変するので、喜んで食べていてもあげるのは規定量の2倍までにする。
- アレルギー素因がある場合は、早く与えるほどアレルギーになりにくいとされている。
離乳中期(生後7~8ヶ月・モグモグ期):1日2回
- 離乳中期について
-
- その後を左右する一番大事な時期!ここが軌道に乗らないと3歳頃まで悩むことも。
- 舌は前後+上下に動くので舌で上あごに押し付けつぶして食べる、絹ごし豆腐状の固さ。
- この動きは結構疲れるので泣いてしまうこともあり、母乳・ミルクで補ってあげる。
- 離乳食のあげかた
-
- 力が入るように、足が着くような椅子に座らせる。
①平らなスプーンを下唇に乗せ、上下の唇ではさみとらせる。こぼされても良いので、口の奥まで入れないようにする。
②手づかみ食べを十分にさせる。
- 手づかみ食べについて
-
- 一口量を学ぶため、スティック状ではなく赤ちゃんせんべい状が好ましい。
例)肉円盤状、輪切りの人参、すいか・桃、ロールパンの輪切り(→パンは喉に詰まりやすいのでトーストorぬらす)、りんご(→りんごはすりおろしでも繊維が多くて喉に詰まりやすいので、必ず加熱する)
離乳後期(生後9~11ヶ月・カミカミ期):1日3回
- 離乳後期について
-
- 舌は前後+上下+左右に動き、歯ぐきの舌と頬ではさんでかめる(一方の頬が大きくふくらむ)。モンキーバナナ状(大人の親指)にする。
- 離乳食のあげかた
-
- テーブルと近づけて手が届くように座らせる。
離乳完了期(生後12~18ヶ月・パクパク期):1日3回+おやつ1~2回
- 離乳完了期について
-
- 舌は自由自在、前歯で噛み切れるので肉円盤状の手づかみメニューを用意する。
- 離乳食のあげかた
- 肘が付くように座らせる。前歯でかじりとらせる。時間栄養学上は朝~夜の食事時間が12時間に収まるのが理想(7時→19時)。
与える食品について
- 食品の種類
-
- 米粥→野菜→豆腐・白身魚・固ゆで卵黄→赤身魚(まぐろ・かつお)・青皮魚(いわし・さんま)・全卵(7ヵ月~)・脂肪の少ない肉・ヨーグルト・チーズ・緑黄色野菜
- 大規模調査で青皮魚を与えられた子ほど脳に良い影響があることが分かっている。
- 脂肪を分解できる膵リパーゼは2~3歳頃から発達するので油っぽいものは与えない。
- 冷凍品は、家庭の冷凍庫だと油脂が酸化しやすい&細菌が生き残っているので1週間以内に食べる。
- ボツリヌス菌は通常の加熱調理では生き延びる(120℃4分)ため、はちみつ入りのパン・菓子・黒砂糖もNG!
- 食物アレルギーについて
-
- 血液検査ではまだ「疑い」の段階なので、アレルギー専門医の下で食物除去試験・食物負荷試験まで行って食べられる許容量を見つけた方がよい。
- 経口摂取からはアレルギーになりにくい。バリア機能が壊れた炎症のある皮膚から食品成分が侵入することで異物とみなされ、抗体が作られることが原因と考えられている。
- 貧血について
-
- 牛乳は鉄が少ないので乳汁の代替にはしない。母乳ばかりでも完了期は鉄分不足になりやすい。
- 鉄欠乏性貧血が3ヶ月以上続くと、貧血が改善しても精神運動発達遅延のリスクがある。
- 鉄を多く含む食材、強化食品、鉄鍋(錆は問題ない)などを活用する。
- ビタミンDは完全母乳だと不足しやすい(UVcut、魚不足)。鮭・さんま・しらす干し、きのこは日光で干すと良い。ビタミンDの合成に必要な日光照射量:夏4-5分、冬20-30分@つくば
- 食器具について
-
- 虫歯になるので哺乳瓶・母乳・育児用粉ミルクは1歳まで。1歳以降はコップを使う。
- 舌の機能は奥から尖端へ発達していき、コップを使わないと舌の尖端の機能が発達せず、言語発達に影響する。ストローマグの使用頻度と時期に注意する。
まとめ
今回、離乳食を本格的に始める前に離乳食教室に参加して、離乳食を進めるうえでの細かい注意点やポイントなどを理解することができました。
専門的な内容をたくさん知れてためになったので、港区のママパパはぜひ参加してみてくださいね◎
離乳食を進める実感が湧いたことで、これからベビーがごっくん→もぐもぐ→かみかみ→ぱくぱく、と色々な食品を食べられるようになるのか~とワクワクしてきました!
 Serena
Serena今まで口にしたことのないものを食べるなんて、ベビーが一番不安ですよね。
ベビーが楽しんで味覚の世界の広がりを楽しめるよう、一緒に感動を共有しながら楽しく付き添いたいなと思っています。